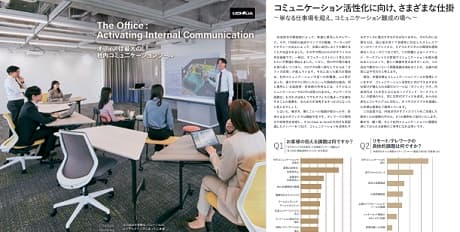- オフィス分野
- 働き方改革(働き方変革)
- コラム
- 第8回:マネージャーの仕事とは 2
第8回:マネージャーの仕事とは 2 【澤円の連載コラム】

いま、働き方が再定義されようとしています。テレワークから出社回帰、働く場も多様化し人とのかかわり方も変わっていくなか、自分らしく、よりハッピーに働くにはどうしたら良いのでしょうか?連載コラム「働き方の再定義 ~なりたい自分になるためのヒント~」では、株式会社圓窓 代表取締役 澤円(さわ まどか)さんと一緒に「はたらく」について考えていきます。
こんにちは、澤です。
前回に引き続き、マネージャーの仕事について考えてみたいと思います。
前回は、「メンバーが全力で仕事に向き合えるようなコンディションを整える」というお話をしました。
職場に存在する様々なボトルネックを取り除き、他部署との連携をするための調整などを行い、メンバーが自分の仕事を完遂できるような環境を作ることこそが、マネージャーの仕事であるとお伝えしました。
今回は、もう一つの大事な仕事についてお伝えします。

ボクがマイクロソフトに勤め始めて間もないころ、「プロジェクトの回し方」というフレームワークを学ぶ機会がありました。
その中で、もっとも印象的だったのは以下の3つの基本原則でした。
- まずプロジェクトのビジョンを決めること
- メンバー全員でそのビジョンに合意すること
- プロジェクトがうまくいかなくなったら、後戻りせずビジョン策定からやり直すこと
どんなプロジェクトであっても、とにかく「ビジョン」を決めることを徹底せよ、という考え方が新鮮であり、かつ納得感がありました。
ビジョンはゴールとは違い、何らかの数値目標ではなくもっと概念的なものでした。
これを「北極星」とも呼んでいました。
北極星はその昔、船乗りたちにとってゴールではなく目印でした。
その目印に当たるのが、プロジェクトのビジョンだったのです。
「全従業員がより早く情報を入手できるデータベースを作る」
「経営判断に必要なデータが一覧できるダッシュボードを開発する」
「いつでもどこでも仕事ができるデバイス環境を実現する」
これくらいの粒度でビジョンは策定され、そのうえで「スコープ」と呼ばれる具体的なアクションが設定されました。
どんな製品を選ぶのか、どのような画面デザインにするのか、どのようなサーバー構成にするのか・・・これらを決めて、ビジョンを実現するためにチーム一丸となってがんばるわけです。
とはいえ、仕事をする上で意見が割れたり、人間関係がぎくしゃくしたりすることもあります。
こういう問題にぶち当たった時こそ、「ビジョンはこっちだよね、まずこのビジョンを目印にしようじゃないか」と、原点に立ち戻ることができるわけです。
この考え方に触れたのは、もう30年近く前のことではありますが、チームマネジメントをする上でも、非常に有効な考え方だよな、と思うんですよね。
コロナ禍を経て、世界中でリモートワークが一気に浸透しました。
その中で、「仕事をすること」と「会社に行くこと」が切り離され、組織に属しているというマインドに大きな変化が生まれました。
結果として「会社という一つの塊ではなく、個人がつながって仕事をしている」というマインドが醸成され、「指示命令系統」に対する考え方がアップデートされました。
さらに、生成AIの発達により、「正しい作業指示」はAIの方がいいという考え方がだんだん一般化されつつあります。
まさに今、人間がやる仕事は何なのか、マネージャーをやる意味は何なのかを見直す時期に来ているんですよね。

ビジョンというのは、人々の「こうありたいな」と思う姿の結晶だと考えています。
それを決めるのは楽しい作業ですし、AIは「ありたい自分」を定義するマインドは(今のところ)ありません。
だからこそ、人間がビジョンを決めて、その方向への舵を切ればよいわけです。
「AIも重要な経営判断をサポートしているではないか!」という意見もあるでしょう。
ただ、AIは「やりたいからやっている」わけではないんですよね。
- AIはビジョンを「決める」ことはできるが、「生み出す」ことはできない
- AIはビジョンを「選ぶ」ことはできるが、「望む」ことはできない
だからこそ、ビジョンを決めるのは人間の聖域だと思うのです。
マネージャーの仕事は、この「ビジョンを決める」ためのプロセスを進めることです。
合意を得るためには、周囲の理解も得ながらことを進めていく必要があります。
チームのメンバーは当然ですし、関係部署やパートナー企業との調整なども含まれます。
「こんな世界を作ろう」ということを考えるのって、楽しくないですか?
そう、実はAIが発展すればするほど、楽しい仕事だけが残ると定義してもいいくらいなんです。
もちろん、今の時点で楽しいと思っている様々な作業がAIに代替されることもあるでしょう。
しかしながら、面倒な作業はまかせて「こうなるといいな~」ってことを考える時間が増えるのは、なかなか幸せなことではありませんか?
「え?そんなのきれいごとでしょ?」ってお思いになるかもしれませんが、きれいごとを馬鹿正直にやることほど、素晴らしい仕事はないと思います。
現実世界、あれこれあります。そりゃそうです。
でも、それにばっかり目を向けたり、手を煩わせたりするのはつまらないですよね。
それもふまえて、明るい未来を作ろうとする人が、世界を変えると思うわけです。

例えば、テスラを例にとってみましょう。
テスラは、2003年創業、2006年に最初のモデル「ロードスター」を発表し、2008年から販売を開始しました。
当時、テスラを「自動車産業を脅かす存在」と認識する自動車会社はありませんでした。
しかし、2024年12月時点でのテスラの株式総額は、ほかのすべての自動車メーカーの株式総額の合計金額を上回りました。
「最近はEVのマーケットが厳しくなってるから、テスラ一強ではなくなる」という見方もありますが、そもそもテスラのビジョンは「自動車産業の中でトップになる」というものではありません。
テスラのビジョンは「持続可能なエネルギーへの移行を加速する」ことであり、自動車産業でトップになることを掲げているのではないのです。
そのビジョンが明確でぶれないからこそ、社員は一丸となって働くことができており、世界でも多くのファンを魅了しているということなのでしょう。
1994年に出版された『ビジョナリー・カンパニー(原題: Built to Last)』では、「なぜ偉大な企業は長期的に繁栄し続けるのか?」 という疑問に対する答えが記されています。
優れたビジョンがあれば、長期的に成功することができ、さらにはカリスマ的なリーダーが存在しなくても繁栄を続けることができると書かれています。
マネージャーは、カリスマ的存在になる必要はなく、ビジョンを作る発起人の役を担えばよいのです。
実際には「作って終わり」ではなく、継続するための努力も不可欠です。
といっても、まだまだマネジメントの仕事=ビジョンを決めること、という考え方が浸透しているとは思えないんですよね。
ということで、まずはビジョンを決める素敵な仕事を楽しんでみましょう。

「え?でも何からやればいいの?」って思う方もおられますよね。
そんな方に、ボクが大好きだったMicrosoftのCMでのフレーズを紹介します。
「Where you want to go today?」
中学校の英語の教科書の例文のようですね。
でも、この言葉って、なかなかいい響きだと思うのです。
「今日どこ行きたい?」って、なんかワクワクしますよね。
この問いかけを、メンバーにしてほしいのです。
もちろん、「Today=今日」に限定する必要はありません。
「Tomorrow=明日」「Future=未来」に置き換えればOKです。
「どこ行きたい?」って相談するの、なかなか楽しくないですか?
▽最新情報をメールでお届け!メールマガジン(無料)にぜひご登録ください!
メルマガに登録して新着コラムを読む
[2025.3.19公開]
こちらの記事もご覧ください
- PICKUP!

オフィスラウンジとは? ~交流を生み出し価値創造へ2025.1.23
社内コミュニケーション オフィスデザイン -

ABWで実現するウェルビーイングなオフィスとは2025.11.4
従業員の働きやすさ 生産性の向上 オフィス環境の改善 -

第16回:なりたいものになるためのAI 【澤円の連載コラム】2025.10.28
動画生成AI キャリアデザイン -

オフィスレイアウト成功の秘訣!種類から進め方まで徹底解説します2025.10.24
オフィスリニューアル 最適なオフィスレイアウト 社内コミュニケーション 生産性向上
- お電話での
お問い合わせ -
- フリーダイヤル
- 0120-077-266
- 祝祭日を除く月曜日から金曜日
午前9時~午後5時