株式会社 北海道新聞社 様本社移転 事例紹介
「第二の創業」と位置付けた本社移転を機に、培ってきた伝統・信頼と、未来への挑戦・変革の両輪で、新時代を拓くワークプレイスを創出
第38回日経ニューオフィス賞「北海道ニューオフィス奨励賞」受賞
- 業種:
- 情報通信業(新聞業)
- 入居人数:
- 約760名(グループ会社除く)
- 面積:
- 約8,500 ㎡
新聞離れやメディアの多様化を背景に、多くの新聞社が大きな転換期を迎えている今日。株式会社北海道新聞社様(以下、道新様)も、将来にわたって北海道を代表する言論・報道機関であり続けるために、さまざまな分野で収益を上げて経営基盤を強固にすることを決意されました。その策の1つが、札幌の一等地にある本社を不動産開発して事業化し、新たな収益源を確立するための移転です。道新様にとって本社移転は1942年の創刊以来初。そこで、「第二の創業」と位置づけ、単なる物理的な移動ではなく、新しい働き方を実現する貴重なチャンスと捉えてプロジェクトをスタートされました。
内田洋行は、全国を網羅するネットワークを生かして北海道支店と東京本社メンバーが連携し、社員の皆様への意識調査から、空間設計、ICTや什器の調達、オフィスマニュアルの作成、および移転後のフォローまで、道新様の「第二の創業」をトータルにご支援いたしました。
- 膨大な紙資料・紙書類、およびICT環境整備の遅れによる業務効率の悪さを解消したい。
- 旧態依然な働き方を改善して、部署間のコミュニケーションを促進したい。
- UCHIDAの強みであるICTソリューションを用いて、Web会議環境の構築など、時代に即したICTをご提案。
- フリーアドレスを基本としたABWへのシフトをご支援。働く場を柔軟に選択でき、部門を超えたコミュニケーションも活性化する執務エリアをご提案。
ポイント紹介
「3Cs」というワークプレイスコンセプトのもと、社員同士が垣根を越えて協力・連携し、会社の総合力を発揮して新たな価値を創造する働き方を追求
道新様は、新本社移転に向けて各職場の幹部で構成する「新本社検討協議会」を設置し、その下に「業務デジタル化」「オフィス空間」「システム」「メディアセンター機能」「移転作業」「グループ社」の6つの部会を設けました。オフィス構築はオフィス空間部会が中心となって活動し、不動産開発室と経営管理局が連携して業務を進めました。
道新様の旧本社は、1979年竣工の建物でもともとは印刷工場を併設していたオフィスのため(印刷工場は1997年に近郊に移転)、構造や設備の面でさまざまな問題があったといいます。「中でも大きな課題は、各部門が個室化しており、部屋を隔てる物理的な壁が心理的にも立ち塞がり、組織のつながりが薄いということでした」と移転当時、不動産開発室でプロジェクトの事務局を務められた大塚敏嗣様。よって、「第二の創業」という意識のもと、ややもすると旧態依然とも指摘される組織風土に風穴を開けるような、新しい働き方の指針を必要としました。
そこで、20代から40代の社員11名のワーキング・グループが考案したワークプレイスコンセプトが「3Cs(スリーシーズ)」です。これは、「Colorful(多様性)」「Connect(つながり)」「Collaboration(協働)」の3つの力が融合することで、次世代につながる Sustainable(持続可能)な組織、新聞社であることを目指す指針。このコンセプトは建物本体の設計にも生かされています。


各階の執務エリアの中央に、人々が集まり行き交う大通に見立てた「boulevarD」を設け、ABWの効果を増進
8階建のビルで本社オフィスが占めるのは4フロア。そのうちの3フロアが執務エリアです。壁や間仕切りの少ない大部屋は、将来的な可変性と維持管理のしやすさを目的にグリッドプランを原則としてゾーニング。席数や機能スペースをグリッドに変換してプログラミングすることで、適正な面積配分を行いました。
そのうえで執務エリアの中央部に複合機をはじめとする共有機器を集約した業務支援エリアを設置し、札幌の街並みのシンボルである大通公園をモチーフに「boulevarD」と命名。作業やクイックワーク、ミーティングができる什器も揃えました。「共用ミーティングテーブルで、異なる部署の人たちが打ち合せや活発な議論を行っている姿をよく見るなど、効果を感じています」と大塚様。
また、本社移転を機に Microsoft365 と全館無線LAN、内線スマホを導入。「ICTは旧オフィスで最も遅れていた部分でした。最初は Teams の操作にも戸惑いましたが、今はこれらのツールなしでは仕事ができない状況です」とヒープ江里子様。なお各会議室にも予約システム、Web会議用機器などICT環境を整え、スムーズかつ有意義な会議ができるご支援をしています。


各フロアに異なる色調の「3C Zone」を設置。ABWの場の1つとしてソロワークやミーティングに、またカジュアルなコミュニケーションにと多目的に活用
執務エリアを抜ける「boulevarD」が行き当たるのは、「3Cs(スリーシーズ)」のコンセプトから生まれた「3C Zone」。ここは、食事やリフレッシュ、打ち合わせ、急な来客対応など多用途に利用できるエリアで、落ち着いて仕事ができるソロワーク席も多数揃えています。フロアごとに、色合いが異なる「3C Zone」は内部階段で行き来が可能。現在は別拠点で勤務されている神力千尋様は「ガラス越しに外が見える気持ちよさもあってか、他の拠点よりも階段を使う人が多い」と感じるそう。上下階のコミュニケーションだけでなく、健康増進にも一役買っています。活発に行き来されている姿は、街の方々にも頼もしく映っているのではないでしょうか。
「移転してから、若手社員を中心にスニーカー、ジャケットのインナーにTシャツといったおしゃれなカジュアルファッションの人が増えたというのも大きな変化です。コロナによる働き方や価値観の変化も影響していると思いますが、オフィスが物理的にも開放的になったことで、気持ち面もとても明るくなったと感じています」とヒープ様。
「新本社は、時代に応じた社員の多様な働き方を支え、想像的な仕事を生み出していく、最新の孵化器=インキュベーターとなるもので、同時に、道民、読者との接点を広げ、『紙とデジタルとリアル』でさまざまな情報を発信していくメディアセンターとしての役割も果たしていきます。移転完了はゴールではなくスタート。どうすれば快適に・効果的に働くことができるのかを、社員一人ひとりが考えてオフィス環境を最大限に活かし、さらに工夫と改善を行ってオフィスを成長させていきたいと考えています」(大塚様)


第38回日経ニューオフィス賞「北海道ニューオフィス奨励賞」受賞
北海道ニューオフィス奨励賞
ご担当者様の声
ご担当者様の声
新聞社のオフィス構築は一般オフィスとは異なる点が多く、組織ごとの独自性も強いため、粘り強いパートナーが必須。丁寧なヒアリングとユーザー視点での提案、柔軟な対応力といった内田洋行さんの知見とご尽力なしでは本社移転はできませんでした。北海道を代表するメディア企業として磨き上げてきたブランド力を存分に生かして、北海道の発展と道民の暮らしの向上に貢献していきたいと考えている当社オフィスの「ありたい姿」を見事に具現化してくれました。
株式会社北海道新聞社
経営管理局 担当部長 大塚 敏嗣 様 (中)
※移転当時は不動産開発室 担当部長
最初は執務室の大部屋化にも抵抗感を示す社員が少なくなかったですが、内田洋行さんがしっかり伴走してくださり、心強かったです。移転後は、違う部署の人たちが近くにいるので、今まで知らなかった他部署の様子がわかるようになり、コミュニケーションがとりやすくなったという意見も多く出ています。新しい価値は、多様な人たちが集まることによって生まれるもの。今後もそれを作り出せる仕掛けを考えていきたいと思います。
株式会社北海道新聞社
不動産開発室 室次長 ヒープ 江里子 様 (左)
移転終了後に私が他拠点に異動になった際、パーソナルロッカーの中の荷物だけの移動で済み、ペーパーレスはこういうところでも効果を発揮するんだと実感しました。今後、本社オフィスをモデルにして、各支社や拠点の設備、働き方を変えていくことが求められます。まだまだ先は長いですが、それが実現してこそ全社一体となったコラボレーションが生まれるのだと感じています。
株式会社北海道新聞社
制作局 担当部長 神力 千尋 様 (右)
※移転当時は管理統括本部付委員
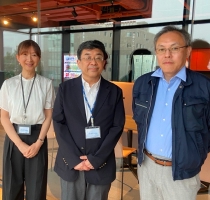
担当営業・デザイナー・PMの声
道新様の「第二の創業」のご支援ができましたことを、誇りに感じております。私自身、過去に商談から移転完了まで3年という案件はありましたが、定例会や個別打ち合わせなどなどで3年間みっちりしっかりご支援させていただいたのは初めてでした。無事に移転が完了した際は私も感無量でしたが、効果が示されるこれからが重要と気を引き締めています。今後も道新様の発展に貢献させていただく所存です。
株式会社内田洋行
北海道営業部 プロジェクトマネージャー 佐藤 洋人
私が北海道に異動してから8年越しで、「北海道を代表する企業様の案件に携わりたい」という思いが実現しました。しかも、中に入る機会がそうそうない新聞社様ということで、打ち合わせで訪問する度に、皆様がお仕事されている様子に私も高揚感を感じました。仕事に誇りを持ってらっしゃるからこそのこだわりを、いかに空間デザインに、しかも公平感を持って取り入れるか。私自身、たくさん学ばせていただいたプロジェクトでした。
パワープレイス株式会社
EDC デザインマネージャー 田村 佳司

お客様について
株式会社北海道新聞社

1942年に道内11紙を統合して「北海道新聞」を創刊以来、北海道専門紙として地域や世代を超え、道民の方々の暮らしをより豊かにする情報やサービスを届け続けている株式会社北海道新聞社様。創刊以来初の本社移転も、創成東地区のランドマークとなり、周辺エリアの活性化の起点となることを目指して計画されました。グループ会社、テナントも入居する8階建のビルの1階には、各種イベントや講演会、演奏会などの開催で、最大200人収容できる交流スペース「DO-BOX EAST」を設置。飲食店2店舗の他、最新記事から北海道の今の動きがわかる大型サイネージなど、地域の方々にご利用いただける施設も備えています。
株式会社北海道新聞社 企業サイト※記事内容は取材当時のものです。(2025年8月取材)
導入された商品・ソリューション
-
 オフィス移転・リニューアルサービス オフィス移転・リニューアルの検討から実施まで、経験豊富な専門家チームが総合的にご支援いたします。経営課題の解決を伴うオフィス移転ならウチダにお任せください。
オフィス移転・リニューアルサービス オフィス移転・リニューアルの検討から実施まで、経験豊富な専門家チームが総合的にご支援いたします。経営課題の解決を伴うオフィス移転ならウチダにお任せください。 -
 オフィスデザイン・構築サービス 組織風土・ファシリティ・ICT・制度と多角的な切り口で、お客様の経営課題に合わせたオフィスをご提案いたします。日経ニューオフィス賞受賞オフィス多数。
オフィスデザイン・構築サービス 組織風土・ファシリティ・ICT・制度と多角的な切り口で、お客様の経営課題に合わせたオフィスをご提案いたします。日経ニューオフィス賞受賞オフィス多数。 -
 ABW/フリーアドレス コミュニケーションを誘発するためのレイアウト、ICTツールの利用、運用方法など、さまざまなノウハウをもとにお客様に最適なABW(アクティビティに応じて、ワーカー1人ひとりが自由に最適な場所を選択する働き方)をご提案します。
ABW/フリーアドレス コミュニケーションを誘発するためのレイアウト、ICTツールの利用、運用方法など、さまざまなノウハウをもとにお客様に最適なABW(アクティビティに応じて、ワーカー1人ひとりが自由に最適な場所を選択する働き方)をご提案します。 -
 AVシステム・ネットワーク(ICT環境)工事 オフィスや公共施設のAV(映像・音響)、ネットワーク(ICT環境)の設計、構築から運用までワンストップで空間づくりをご支援いたします。
AVシステム・ネットワーク(ICT環境)工事 オフィスや公共施設のAV(映像・音響)、ネットワーク(ICT環境)の設計、構築から運用までワンストップで空間づくりをご支援いたします。



























